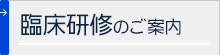[ 臨床研修のご案内 ]
最新情報を更新していきます。
研修医へのメッセージ
┗(カテゴリ)2009年度臨床研修医||Posted:2009-01-28
【尾道市立市民病院長 太田 保】
当院は、尾道市医師会および松永沼隈地区医師会との緊密な連携を行い、十分な地域の医療分担を行っております。
病院には夜間救急センターを併設しており、高度の治療を行う一方で1次救急にも力を入れております。2008年6月から夜間救急診療所は周辺医師会の開業医も参加し、地域一丸となって救急に対応しております。
2008年2月には地域医療支援病院に認定され急性期病院として地域医療に貢献しております。救急隊員の日勤帯の常駐を行い、医師の現場への出動も行っております。2007年2月にはICU、CCU、2007年4月からはベッド数14の透析センターが稼動し、さらに2007年9月には消化器内視鏡センターがオープンしております。
尾道方式の一つとしての退院時ケアーカンファレンスや2週間の診療所での研修もあり、地域医療の研修にも重点を置いております。研修医各自の希望を取り入れた研修カリキュラムはかなりフレキシブルなものとなっております。
指導医には熱意と知識、技能、経験が必要ですが、当院の指導医にはそれが備わっていると確信しております。各科の連携は極めて良く、特に内科、外科、放射線科合同のカンファレンスは週3回あり充分な意見交換を行っております。CPCは年3〜4回、救急症例検討会なども行っており卒後研修に適した病院であります。
日夜、地域の住民が安心できる医療を提供できるよう努力しております。これから当院は「市民を中心とした医療」を大目標とし、がん治療と急性期医療病院として、また地域医療の拠点病院として大きく変わってまいりました。この変革に参加するとともに多くの症例を経験し、美味しい魚を食べて人間性豊かな医師を目指してください。
【臨床研修委員長 藤野 寿幸】
尾道市立市民病院は、尾道市を中心とした診療圏における救急診療や各科専門分野の中核的医療機関として地域医療に貢献しています。尾道は歴史の古い町であると同時に、周辺市町村との合併で瀬戸内の十字路として進展しています。このようななかで、大都市、大病院にはない、環境のよい小回りの利く中規模の病院であり、臨床研修には絶好の条件が整っています。臨床研修プログラムにおいては、これらが有機的かつ緻密に配置され、指導医のもとに現場で通用する臨床医として、プライマリ・ケアと救急医療を第一に習得し、基本的で偏りのない診断、治療への柔軟な対応が可能となるように修練を行います。常時地域住民の診療を担う病院であり、2年間のローテーションを行えばプライマリ・ケアにおいて検査、治療に自信の持てる医師に成長できます。また連日のように行われるカンファレンス、抄読会などに参加し、医師として重要な生涯学習のための基礎を養うことも可能となります。多忙ななかにも、一例一例の症例を大切にして、まとめ上げる能力を付け臨床研修評価に耐え得るものとしています。意欲的でアクティブな者には研修の成果が約束され、ここでの臨床! 経験は医師としての人生に大きな財産となることは間違いありません。
さらに、研修医は1週間のアメリカ研修を行い、2007年1月にミネソタ大学とNIH、12月にMDアンダーソンを見学してきました。また、年1回テネシー大学、マーサー大学の学生との交流会も行っています。これらにより、世界に向けた広い視野も養われます。また、年1回群星研修センター長の宮城征四郎先生、年3〜4回東京医科大学総合診療科の齊藤裕之先生に臨床講義、ベッドサイドレクチャーをお願いしています。ただし、夢を大きく膨らませ医学を現実のものにするためには、継続して修練に励む必要があります。医学は常に進歩するものであり、新しい医療や自己の医療行為に対して、常に批判的で自己確認のうえに行われるべきです。そして、経験を積み、知識や技術を習得したとしても医学・医療の本質は変わらないし、臨床は患者が主体であることを銘記してもらいたいと思っています。
【麻酔科・救急部門指導医(医局長) 突沖 満則】
当院麻酔科は常勤医3名(日本麻酔科学会指導医1名、専門医2名)で年間約900例の全身麻酔症例と、約800例の脊髄くも膜下麻酔症例を行い、そのうち術後鎮痛を目的とした硬膜外麻酔併用例も約450例、完全静脈麻酔も約200例行っています。
救急部門としては、尾道市立夜間救急診療所も併設されており、24時間体制で年間約4500例の救急搬送患者を受け入れています。この地域で発生した1次から3次までのすべての救急患者が対象となり、プライマリ・ケアから重症患者管理まで救急診療に必要なすべての事柄を研修することになります。救急診療部および集中治療部のための新棟が2006年4月に完成し、重症患者の初期治療から手術室および集中治療室への継続治療が可能になっています。また救急診療棟には消防署の救急隊が日勤中に常駐するワークステーションも全国に先駆けて稼動させ、ドクターカーとしての対応も可能にしています。
当院の研修スケジュールとしては、1年次に麻酔科と救急部門を合わせて3ヶ月、さらに2年次には希望により選択することが可能で、より高度な内容を習得することができます。また、尾道市立夜間救急診療所では副直として1年次の研修を行い、内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科等の指導医の監督の下に積極的に診療に携わり、2年次には主当直として1年次の研修医の指導にあたることにより、救急に関する知識、技術の更なる向上に努めます。
やる気のある研修医には見学のみにとどまらず、実技を幅広く身に付けるチャンスがあります。優秀な指導スタッフと一緒に楽しく、かつ真剣に取り組んでみましょう。
【内科指導医(内科診療部長) 水戸川 剛秀】
当院は地域の基幹病院として24時間救急を担っており、研修期間中は常に救急にたずさわっていただきます。このため当院の研修では、自然と豊富な症例を経験できるようになっております。現在、市町村合併によって医療圏が広がり、今後予想されるより多くの救急患者及び重症患者の受け入れのため、救急新棟を増築しました。さらに地域環境から、当院の医療圏には高齢者が増加しており、緩和ケア、医療福祉の分野についても幅広く研修できるようになっております。
研修医時代には、知識・技術の習得に走り勝ちですが、われわれが習得していただきたいのは、知識・技術に偏重しない全人的な医療への姿勢です。
臨床の場で人間として、医師として成熟していってほしいと願っております。医療を行う上でさまざまな考え方を身につけなければ、社会から求められている透明性のある医療、患者に優しい医療などに応えていけないと思うからです。内科の医師は少し減員になりますが、各指導医は多才ですし、研修プログラムの改善は毎年研修医の意見を参考にしながら改定を行っており、330床という大きすぎない病院で各科の連携もよく、コメディカルスタッフも充実しているので初期研修を行うには充分な病院であると考えています。
【外科指導医(外科診療部長) 川真田 修】
当院外科は院長含め常勤医6人(外科学会認定指導医3人)と後期研修医2人のスタッフで年間約450例の全麻症例と約150例の脊麻手術をこなしています。食道癌・肺癌・肝癌・膵癌など高度な手術から虫垂炎やソケイヘルニアまで豊富な症例を有しています。鏡視下手術も積極的に施行しています。後期研修医も実力がつけば悪性疾患も含め指導医の下術者として執刀しています。超音波、上部・下部内視鏡などの検査も行っております。当院は救急疾患にも積極的に対応しており、急性疾患や外傷、プライマリ・ケアも十分に学べます。消化器、肝胆膵、呼吸器の各領域に専門医がおり各学会の臨床研修病院にも指定されています。大病院にない家庭的な雰囲気の中、内科・放射線科とのカンファレンスも週1回臓器毎に行っています。食べ物も美味しい風光明媚な尾道で腕もお腹も大満足の研修ができると自負しています。真の外科医を目指す諸君のお越しを心からお待ちしております。
【研修医(2年目) 池田 佳寿子】
尾道市立市民病院での研修も早2年目を迎えましたが、この1年間、大変内容の濃い研修が行えたと思っています。研修医の数は少ないですが、その分、研修科を超えて色々な先生方から声を掛けていただき、様々な手技も積極的にさせていただきました。どの科の先生も、当直や日々の診療の際に分からないことがあれば、どんな些細な疑問でも親切に細やかに教えてくださいます。また、朝の画像カンファレンスや研修医の為の勉強会も定期的に開かれ、診療以外でも勉強の場は沢山設けられています。
この病院での研修は、「やる気さえあれば、いくらでも成長できる」研修内容・研修環境だと思います。確かに壁にぶつかり、自分の力不足に悩むことは多々ありましたが、先生方、先輩の研修医の先生方、コメディカルスタッフの方々、時には患者さんに支えられ、1年間で大きく成長できたように思います。やる気のある方々、このアットホームで温かい尾道市立市民病院で一緒に研修してみませんか?